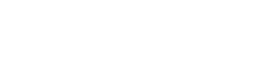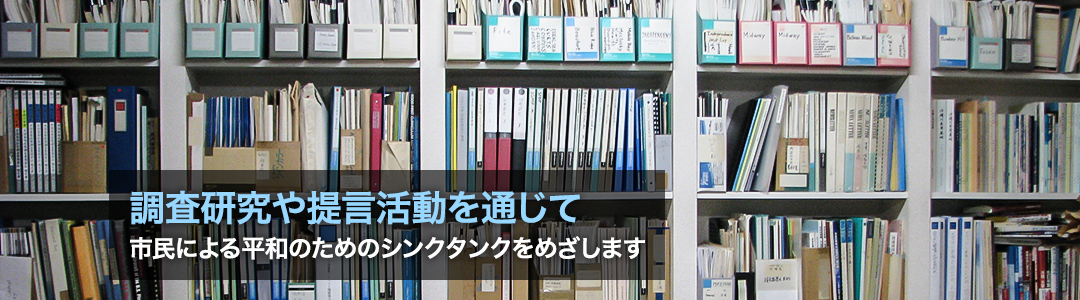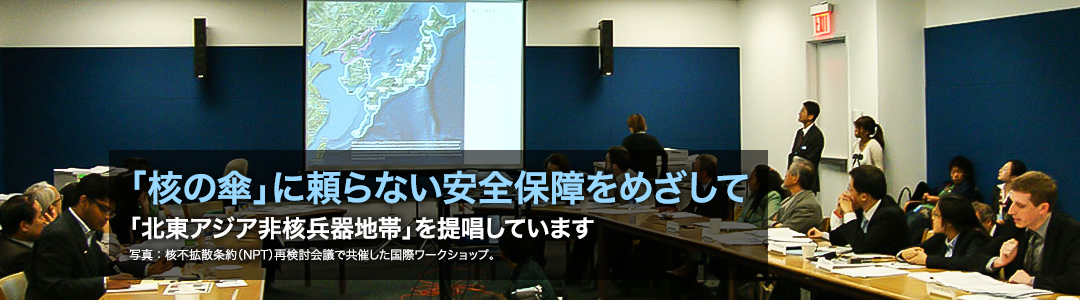鈴木達治郎氏、ピースデポ新代表に就任
 2025年3月31日まで長崎大学核兵器廃絶研究センター教授を務めた鈴木達治郎さんが4月1日よりピースデポ代表に就任しました。以下では新代表のプロフィールと「脱軍備・平和レポート」第32号に掲載された所信表明「ピースデポ代表に就任して」を転載します。
2025年3月31日まで長崎大学核兵器廃絶研究センター教授を務めた鈴木達治郎さんが4月1日よりピースデポ代表に就任しました。以下では新代表のプロフィールと「脱軍備・平和レポート」第32号に掲載された所信表明「ピースデポ代表に就任して」を転載します。
鈴木達治郎(すずき たつじろう)さんプロフィール
1951 年生まれ。75年東京大学工学部原子力工学科卒。78年マサチューセッツ工科大学プログラム修士修了。工学博士(東京大学)。専門は原子力政策、核軍縮・不拡散政策、科学技術と社会論。2010年1月より2014 年3月まで内閣府原子力委員会委員長代理を務めた。2014年より長崎大学核兵器廃絶研究センター教授。2015年より19年までセンター長。核兵器と戦争の根絶を目指す科学者集団パグウォッシュ会議評議員、および2025年から執行委員会委員長として活動を続けている。
ピースデポ代表に就任して
この度、4 月 1 日付で、ピースデポ代表に就任させていただきました、鈴木達治郎です。長い歴史を持つ伝統ある市民団体として、以前からその活動には高い敬意と関心を持って注目してきました。その団体に、この度縁あって代表として就任することになり、身の引き締まる思いでいっぱいです。
私は、大学で原子力工学を専攻しましたが、修士課程から米国マサチューセッツ工科大(MIT)で「技術と政策」プログラムに移動し、そこから一貫して技術政策、とくに技術が社会に及ぼす影響と、原子力と核兵器との関連に取り組んできました。2010 年1月から 2014 年3月末まで、民主党政権下で政府の原子力委員会委員長代理を務め、その間に東京電力福島第一原子力発電所の事故を体験しました。これが原子力発電のもつリスクへの考えを根本的に見直すことにつながり、その後は「原子力発電に依存しない社会」を目指すべきと考えが変わりました。また、福島原発の廃炉・復興はもちろんのこと、核のゴミ問題や、核燃サイクル問題など原子力がこれまでもたらしてきた「負の遺産」への取り組みを最優先すべきと主張してきました 。
2014 年 4 月から 2025 年 3 月まで、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)の教授として、核軍縮・不拡散問題にとり組んできました。梅林初代センター長の後をついで、二代目のセンター長として 4 年務め、その後も RECNAのスタッフとして、主に北東アジアの非核化プロジェクトや、核弾頭・核物質のデータベースを担当してきました。また、個人的には、戦争と核兵器の根絶を目指す科学者団体「パグウォッシュ会議」の活動にも参加してきており、今年1月には執行委員会委員長という役員にも就任いたしました。他には、国際核物質専門家パネル(IPFM)の共同議長、アジア太平洋リーダーシップネットワーク(APLN)の諮問会議メンバーや、最近では国連軍縮研究所(UNIDIR)のシニア・フェロー就任など、核軍縮問題には広く従事してきております。
その中で、今最も重視している課題は、「核抑止」と「核の傘(拡大核抑止)」という、核兵器の存在を正当化している理論とどう戦い、それに代わる安全保障政策をどう構築していくか、という問題です。世論調査をみても、核廃絶には賛成だが、当面は「核抑止や核の傘が必要」と考えている人が多数、というのが現実です。特に、ロシアのウクライナ侵攻後は、核兵器の脅威が強調され、80年続いてきた「核のタブー(不使用)」がいつ壊れるかもしれない、という状況にあるため、核兵器の使用を防ぐために「核抑止」が必要との考えが、多くの人たちに共有されてしまった感があります。
どうすれば、この状況から脱却できるか。これが今、私の最大の問いであり、おそらく「ピースデポ」のメンバーの方々も感じておられる共通の課題ではないでしょうか。 先日、核兵器禁止条約(TPNW)の第3回締約国会議に初めて参加する機会を得ました。そこで、本気になって核兵器廃絶を目指す政府の代表、専門家、そして市民社会の人たちと同じ場で交流することができたのは、大きな経験でした。なかでも、科学諮問グループ(SAG)の活躍ぶりには大変感銘を受けました。今回 TPNW は、従来の「人間の安全保障」という観点からのみならず、核依存国との対話を進めるべく、あえて「国家安全保障」という観点からも核兵器の問題を取り扱うことを決め、とくに「核抑止論」に正面から取り組むことになりました。その中で、「科学的根拠」に基づく分析を重視することになり、SAG の役割が非常に重要となりました。中でも注目したのは、SAG 座長のジア・ミアン博士の発言で、「核兵器をなくすためには、それを支えている社会構造そのものの変革が必要だ」というものでした。すなわち、核兵器を支える社会構造、具体的には法制度、産業組織、研究開発機関、教育機関など、あらゆる社会要素を根本的に排除する必要がある、という画期的な考え方でした。この考えは、80年続いてきた核兵器を支える社会構造への挑戦であり、極めて野心的な目標ではありますが、確かに核兵器をなくすにはそれだけの「社会革命」を必要としているのでしょう。まさにパラダイム・シフトを起こすことを意味しています。
振り返って、現実の社会ではトランプ政権の外交政策が、別の意味でこれまでの国際秩序を次々と破壊しています。北東アジアでは、中国や北朝鮮の核の脅威に対抗して、日韓米の軍事同盟がますます強化されつつあります。このままでは、核抑止の強化が更なる核軍拡を生み出す「悪のサイクル」が拡大していく可能性が大です。北東アジア非核兵器地帯を一つの手段として、地域の平和と安全保障を確保するという、ピースデポがこれまで取り組んできた活動をより一層充実させなければいけません。それが「核抑止に依存しない安全保障政策」の確立に貢献することは間違いありません。
厳しい安全保障環境にあるからこそ、「核抑止」という「誤謬の理論」(TPNW 政治宣言)に挑戦することが必要です。その中で、専門家としてまた市民社会の一員として、「ピースデポ」の力がますます求められています。微力ではありますが、皆さんと一緒に、この厳しい状況のなか、核兵器と戦争の根絶を目指して、取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
脱軍備・平和レポート第32号(2025年4月1日)

[講義録]2024年度 第5回「脱軍備・平和基礎講座」
パレスチナの人びとの平和的生存権と日本の役割 清末愛砂
ピースデポ代表に就任して 鈴木達治郎
《ユース・ムーブメント~核兵器をなくす私たちの取り組み》第5回
ジェンダーの視点から核兵器廃絶を目指す――多様なユースのかかわり方を模索する 徳田悠希
[特別寄稿]残された課題――日本被団協は、なぜ国家補償を求め続けるのか 足立修一
[報告]2025年度防衛予算に関する2・18 防衛省交渉――ミサイル配備とイージス艦の建造に多額の費用 木元茂夫
トピックス
● 2025 年の「終末時計」、過去最短の人類滅亡まで残り89 秒
● 核軍縮をめぐるトランプのイニシアチブと中国、ロシアの反応
● 馬毛島の工事-計画の杜撰さが明らかに
● イスラエル、停戦合意破りのガザ攻撃再開
連載 全体を生きる(54)
反トマ運動の始まり(3)核チェック 梅林宏道
平和を考えるための映画ガイド
子守唄を歌う子、死に歌を歌う子――『太陽の帝国』
日誌 2025年1月16日~3月15日
新着情報
-
2025.04.02
-
2025.04.01
-
2025.02.01
-
2025.01.24
-
2024.12.01